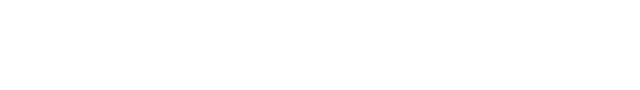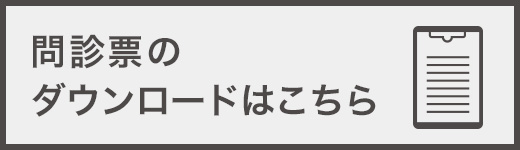ステロイド全身投与のデメリット
ステロイド全身投与のメリットとデメリット
ステロイド(副腎皮質ステロイド)は、強力な抗炎症作用と免疫抑制作用を持つ薬剤であり、多くの疾患に対して治療効果を発揮します。
私は呼吸器内科医であるため、吸入のステロイド薬を頻繁に処方します。
一方でステロイドの全身投与を可能な限り避けるように他の薬剤を工夫しながら処方しています。
なぜならステロイドは全身投与(経口投与や静脈注射など)により、局所投与では届かない全身性の病態に対応できる点が大きな利点である一方で、全身に作用するため副作用も多岐にわたるからです。
ステロイド全身投与のメリット
1.抗炎症作用の即効性と強力さ
ステロイドは炎症性サイトカインなどの産生を抑制し、白血球の活性や浸潤を抑えることで、炎症反応を劇的に鎮めます。急性期の重症疾患では、即効性のある治療手段として不可欠です。
2.自己免疫疾患に対する効果
自己免疫が暴走してしまう疾患である膠原病において、免疫反応の過剰な活性を抑えることで、症状の緩和と組織破壊の進行を防ぐ効果があります。特に導入期には高用量を用いて早期にコントロールを図る場面もあります。
3.移植医療での拒絶反応予防
臓器移植後における急性拒絶反応の抑制にも用いられます。ステロイドによる免疫抑制作用は、移植片を異物として認識しないように免疫系をコントロールするのに有効です。
4.がん化学療法との併用
一部の血液がんでは治療薬の一部として使用されるほか、化学療法に伴う悪心・嘔吐の予防や、脳腫瘍による浮腫の軽減にも効果を発揮します。
■ 全身投与のデメリット(副作用)
1.感染症リスクの増加
免疫抑制作用のため、細菌・ウイルス・真菌・寄生虫などによる感染症の発症リスクが高まります。特に結核や帯状疱疹、ニューモシスチス肺炎(Pneumocystis jirovecii)など、通常では発症しにくい病原体による感染に注意が必要です。
2.代謝系への影響(糖尿病・脂質異常)
糖新生の促進やインスリン抵抗性の増加により、血糖値が上昇し、糖尿病の発症や既存の糖尿病の悪化を引き起こすことがあります。また、脂質代謝にも影響し、高脂血症や動脈硬化の進行に関与します。
3.骨代謝異常と骨粗鬆症
ステロイドは骨吸収を促進し、骨形成を抑制することで骨密度を低下させます。長期投与では骨粗鬆症や骨折(特に椎体圧迫骨折)のリスクが高くなります。
4.消化性潰瘍
胃粘膜保護因子の減少や胃酸分泌促進により、消化性潰瘍や胃出血のリスクが増加します。NSAIDsとの併用ではさらにリスクが上がります。
5.精神・神経症状
高用量使用時には精神症状(不眠、気分高揚、うつ、精神病様症状)が出現することがあります。特に高齢者ではせん妄などのリスクも高くなります。
6.副腎不全
ステロイドの長期投与により、視床下部-下垂体-副腎系が抑制され、体内での副腎皮質ホルモン産生が低下します。突然の中止やストレス時には、副腎不全(特に二次性副腎不全)を生じ、倦怠感、低血圧、低血糖、ショックなどを引き起こすことがあります。ステロイドの内服薬を自己調節してはいけません。医師の指示に従って徐々に減量する必要があります。
7.その他の副作用
・皮膚萎縮・紫斑・にきび:皮膚が薄くなり、脆弱化する
・筋萎縮・筋力低下:特に近位筋に影響
・体重増加・満月様顔貌・中心性肥満(クッシング症候群様)
・白内障・緑内障:眼科的フォローが必要
良く処方されるステロイド薬
ステロイドの内服薬/注射薬にどんなものがあるか知らない方も多いと思います。自分のお薬手帳や注射伝票を眺めて以下の薬剤名があった場合には、その薬剤のメリットとデメリットを知っておくことをお勧めします。
ケナコルト(トリアムシノロンアセトニド)
メリット:強力で長時間作用型のステロイドであり、関節炎やアレルギー性鼻炎、皮膚疾患などに対して効果が持続します。特に花粉症注射として使用される場合、1回の筋注で数週間から数か月効果が持続するため、利便性が高い点が評価されます。
デメリット:長時間体内に残留するため、副作用(副腎抑制、高血糖、感染症リスク、皮膚萎縮など)が長期間にわたって持続する恐れがあります。
補足:花粉症に対する自費診療として用いている医療機関もあります。花粉症対策として1回の筋肉注射(ケナコルト40mg)を用いた場合の自費価格は都内・都市部で約3,000〜7,000円であり、一部の美容クリニックなどでは10,000円以上の例もあります。因みにケナコルト-A筋注用40mg(1バイアル)の薬価は約370円です。
自費診療の場合は有害事象が起きても責任を取らないという内容が記載された承諾書にサインをした上で約370円の薬剤を高い金額で注射されます。
自費診療は何か起きても自己責任になります。投与される前によ~く考えることをお勧めします。
個人的には全くお勧めしません。
デカドロン(デキサメタゾン)、リンデロン(ベタメタゾン)
メリット:強力で持続的な抗炎症・免疫抑制作用があり。少量で効果が期待できます。
デメリット:作用時間が非常に長く、副腎抑制や血糖上昇などの副作用が持続しやすいため、短期使用でも副作用が出やすく、慢性使用には注意が必要です。
セレスタミン配合錠、ベタセレミン配合錠、ヒスタブロック配合錠(ベタメタゾン+d-クロルフェニラミン)
メリット:ステロイドと抗ヒスタミン薬の合剤であり、アレルギー性鼻炎や蕁麻疹などの症状に迅速かつ強力に効果を発揮します。内服で使いやすく、短期的な症状緩和に有効です。
デメリット:ステロイドの全身性副作用(血糖上昇、胃潰瘍、免疫抑制など)と、抗ヒスタミン薬の副作用(眠気、口渇、排尿困難など)を併せ持つため、長期連用には適さず、漫然投与に注意が必要です。
補足:個人的な印象では処方頻度は耳鼻科>>皮膚科>内科といった感じです。上記の配合剤には、ベタメタゾン(0.25mg)が1錠中に含まれています。ベタメタゾン 0.25mg はプレドニン 約1.67~2.5mg に相当します。2錠だと3.34~5mg、4錠だと6.68mg~10mgのプレドニンを使用しているのと同じことになります。
シロップの製剤もあるため小児に対して安易に処方する医師もいるようですが…個人的には全くお勧めしません。
プレドニン(プレドニゾロン)
メリット:中等度の抗炎症作用と免疫抑制作用を持ち、自己免疫疾患や喘息、腎炎など幅広く使用されます。作用時間も適度で、長期管理に適しています。
デメリット:長期使用で副腎機能抑制、骨粗鬆症、糖尿病、感染リスク上昇などの副作用があり、減量時は離脱症状に注意が必要です。
補足:生理的に分泌される副腎皮質ホルモンはプレドニンに換算すると3.75mg程度と言われています。
コートリル(ヒドロコルチゾン)
メリット:生理的コルチゾールに近く、置換療法(副腎不全など)に適しており、急性ストレス対応にも用いられます。作用時間が短く調整しやすいです。
デメリット:抗炎症作用は弱いため、重症炎症疾患には不十分なことがあり、1日数回の投与が必要です。大量投与時は他のステロイドと同様の副作用が出ます。
補足:他のステロイド長期使用により副腎皮質ホルモン産生低下が起きてしまった際にやむを得ず長期使用する際に用いることが多い薬剤です。薬剤による副腎皮質ホルモン産生低下の敗戦処理的に投与する機会が多いため、処方頻度は内科>>他科といった印象です。
まとめ
ステロイドの全身投与は、炎症性疾患や自己免疫疾患、移植、腫瘍性疾患など多岐にわたる疾患に対して非常に強力かつ有効な治療手段です。
急性期のコントロールや寛解導入には欠かせない一方で、全身性の副作用が多いため、必要最小限の用量と期間で使用し、可能であれば速やかに減量・中止することが理想とされます。また、治療中は副作用のモニタリングや、骨粗鬆症・感染症・糖代謝などへの予防的対応も重要です。
我々呼吸器内科は喘息発作などに対してステロイドの全身投与をすることがあります。
年4回以上の全身ステロイド投与を行うと10年間の観察で合併症が1.29倍増加し(Sullivian PW et al. JACI 2018 141;110-116)、かえって合併症の医療費の方が嵩んでしまうということが報告されているため、極力全身ステロイド投与を行わないで済むように配慮しながら薬剤選択をしています。
しかし、他院/他科で安易に全身ステロイド投与をされていた事をお薬手帳で見つけてしまうことが結構あります。
安易に長期間全身ステロイド投与が行われてしまったことによって糖尿病などの悪化や副腎皮質ホルモン産生低下をきたしている患者さんを見つけてしまったりすると非常にやるせない気持ちになります。
ステロイドは適切な使用により患者のQOLや予後を大きく改善できる薬剤である一方で、「諸刃の剣」としての一面があり、副腎皮質ホルモン産生が一度低下しまうとその内分泌障害はなかなか改善しません。
医師だけでなく患者さんも長期的なステロイド全身投与には色々な副作用があることを知っておくべきだと考えます。