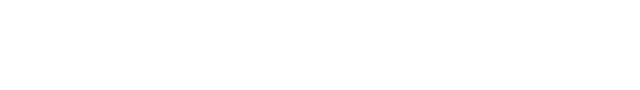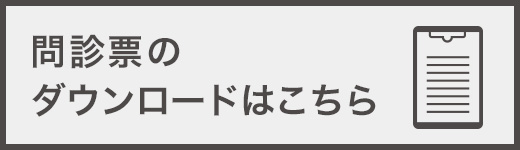Medical Practice (MP)2024年11・12月号
文光堂さんからMedical Practice (MP)の2024年11月号、12月号の献本が届きました。
届いた理由は私がOne Point Advieのコラムに「慢性咳嗽-診断のポイントと盲点-」という依頼原稿を書いたからです。
今回の院長ブログはこの依頼原稿について記載します。
依頼原稿作成の経緯
以前私は文光堂から発刊された「おとなの食物アレルギー」「おとなのアレルギー 皮膚科コラボ編」の原稿の一部と挿絵全般をかきました。
大人の食物アレルギーについてはこちら?
大人の食物アレルギーの記事と本 | 中村橋いとう内科クリニック
この際に知り合いになった編集者さんからお手紙が3月末に届きました。
手紙の内容はMedical Practice (MP)のOne Point Advieの執筆依頼でした。
MPのOne Point Advieは実地臨床に直接役立つアドバイスを硬い論文調ではなく、肩の力を抜いて読めるように複数の医師が下記の内容を800字程度にまとめたコラム形式の読みものです。
・検査結果を読むときの注意点
・薬の処方上の注意点
・治療の進歩、新しい検査法、治療法
・診断、治療の意外な盲点・思わずヒヤリとした先生自身の体験
・専門医に紹介するタイミング
・研修医、若手医師への指導の仕方
など
原稿料は高くないですが、編集者さんから手書きのイラストも入っていたお手紙でしたので、2週間以内に「咳」に関する講演会に使用した2つの症例の依頼原稿を書き上げて4月上旬に返信しました。
返信した原稿が採用されてこの度掲載されたという経緯です。
慢性咳嗽の診療
内科を受診する主訴で最も多いのは咳です。3週間未満の急性咳嗽の咳の鑑別は比較的容易です。
しかし、8週間を超える慢性咳嗽の診療は意外に難しいため、残念ながらちゃんとした咳の診療を行う力がない先生は結構多くいます。
日本呼吸器学会から咳嗽診断の補助として2005年と2012年に「咳嗽に関するガイドライン」の初版と第2版が出版されており、2019年に「咳嗽・喀痰の診療ガイドライン」に改良されて出版されています。
呼吸器学会に所属している先生は呼吸器系のガイドラインが自動的に送られてくるので目を通していると思いますが、呼吸器学会に所属していない先生は本屋で購入しないといけないことから、咳に関するガイドラインに目を通さずに咳の診療をおこなっているが咳の診療における力の差につながっています。
ガイドラインよりも簡潔に、患者さんや後輩医師に説明することを目的として診断のポイントを4コマに落とし込んで2020年に作成したのが「咳のことはDr.AIちゃんにきけ!」です。
この本は病棟業務を終えて帰宅した後に夜な夜な描いたので登場人物の描写が乱れに乱れていますが、16種類の咳について解りやすく書いた(描いた)つもりです。
マンガで描けるほど単純な症例でないことも多く、診断に苦慮した慢性咳嗽の患者さんの一部をMPの「慢性咳嗽-診断のポイントと盲点-」で記載しました。
内容が気になる方は本屋で探して読んでください。
依頼原稿について
医師をしていると原稿を書く機会が結構あります。
依頼原稿は大学にいると偉い先生から年に何個か降ってきます。
大学にいると医局の業績アップのために学会発表や論文作成をするようにという圧がかなりあります。
開業医になるとそれらの圧から解放されるのですが、現在でも12月14日(土)に秋葉原で開催される「第12回アレルギー学会関東地方会」で発表される演題を後輩医局員のために作成しており、この症例の論文も作成し始めました。
昨年の書いた依頼原稿などはこちら?
大学の勤務医と違って開業医になると「集患や啓蒙のために自費出版をしないか?面談の時間を作って欲しい」という話が複数の会社からやって来ます。
しかし、この手の依頼は「○○の医療の不都合な真実」とか「本当は怖い〇〇」など商業的にインパクト重視の原稿が求められるため、私は書く気にはなれません。
時間もないので全て断っており、今後も自費出版の話に関しては断る方針としています。