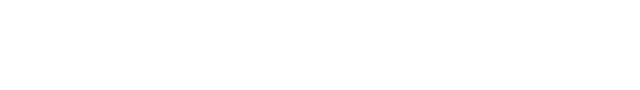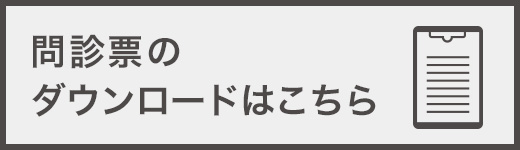コチニールアレルギー
今回の院長ブログではコチニールアレルギーについて記載します。
コチニール色素とは
コチニール色素(カルミン酸)は染料あるいは食品添加物(天然着色料)として使用される赤い色の色素です。
この色素はコチニールカイガラムシのメスの体から抽出して作成されます。
感作経路としては口紅やチークなど化粧品からの経皮/経粘膜感作が考えられています。
残念なことに現時点ではコチニールアレルギーを採血検査で調べることはできません。しかし、アレルギー反応を起こした現物が残っていれば、その食物を用いて皮膚テストで診断をすることが出来ます。
私が出会ったコチニールアレルギーの患者さんは旅行先で購入したマカロンを日本で食べた際にアナフィラキシーを発症して救急搬送され、緊急入院した方でした。
その患者さんはアナフィラキシーの原因となったスイス製のマカロンが捨てずに残していました。
成分表を確認したところ予想通り「Karmin」と記載されていたので、後日マカロンを用いて行った皮膚テストでスイス製のマカロンが陽性、対照として用いた日本製のマカロンは陰性という結果からコチニールアレルギーと診断しました。
コチニール色素はKarmin以外にMK-40、KL-80、E120といった記載をされることもあります。
ちなみにこの患者さんが使用していた化粧品はフランス製であり、化粧品に含まれていたコチニールによる経皮感作が原因によるコチニールを含む赤いマカロンのアレルギーと考えられました。
海外ではまだコチニールの規制が不十分な国もあるため、注意が必要です。
コチニールアレルギーの確定診断をするには
コチニールアレルギーの確定診断にはプリックテストをする必要があります。
しかし、アレルギー症状が出た食物をそのまま取っておく人は少なく、コチニールアレルギーを疑うエピソードがあった患者さんの診断をプリックテストで診断することができないことが多いです。
実際、開業後もコチニールアレルギーが疑われる方を何人か診てきましたが、確定診断をつけることができませんでした。
どうしたらよいかと苦心していた頃に日本画に特化した画材屋さん(得応軒)でコチニールレーキを売っているという情報を得ました。
事前にコチニールを置いてあるかどうか確認のTELをし、近くに東京藝術大学があるのでこういった特殊なお店があるのかな…と想像しながら、暑い夏の休診日に谷中にある得応軒まで自転車をこいで行きました。
お店の店員さんにコチニールを求めている理由を説明したところ、「画材として用いるコチニールレーキは水に溶けない」と言われてしまいました。
水に溶けないのであればプリックテストに用いることができないと肩を落としていた私に対し、店員さんは水に溶かして使いたいのであればコチニールカイガラムシから抽出した方が良いと教えてくれました。
そして、「暑い日にわざわざ来てくれたし医学に貢献するのであれば…」といって奥の棚から取り出してきた少量のカイガラムシを無料で分けてくれました。
コチニールカイガラムシを無料で分けてくださった得応軒の店員さんにこの場を借りて感謝いたします!
【注】コチニールの検査は現物がないとできません。虫から色素を抽出するのも時間がかかるためいつでもできる訳ではなく、時間がかかるため別途予約料も頂くことになります。
プリックテストに関するブログはこちら👇
プリックテスト | 中村橋いとう内科クリニック
日本画の画材
日本画材屋さんにコチニールレーキが売られているようにコチニールは日本画の画材として売られています。
日本画中心に展示してある芦ノ湖にある成川美術館に先日訪れる機会がありました。
成川美術館の方から教えて頂いた知識ですが、日本画に用いられる岩絵の具は非常に高価であり、日本画を学ぶ芸大の学生はバイト代の大半が絵具代になってしまうようです。
例えば青い色は「ラピスラズリ」、緑青(ろくしょう)は「孔雀石」、黄色は「金茶石」、「黄碧玉(きへきぎょく)」といった宝石に用いられるような石を砕いて作られています。
日本画は水に溶けない岩絵の具を和紙にくっつけるために膠(にかわ)を用いて塗るため非常に手間がかかる反面、色の変化が起こりにくいということを初めて知りました。
天然石による岩絵の具は15gで4000~5000円と高額でああり、15gで描ける絵の範囲はそんなに大きくありません。
このように日本画は宝石で描かれているようなものなので大きな絵を買うことはとてもできませんが、クリニック内の展示用に一枚だけ高崎昇平先生の小さな絵を購入してみました。
飾られている絵を鑑賞する際に青はラピスラズリ、緑は孔雀石、赤はコチニールなのか…などと岩絵の具の元になっている鉱物などにも想像を膨らませながら観ると面白いかもしれません。
コロナ禍に入る前に東京藝術大学の文化祭で購入した小さな絵も今後院内に展示しようと思っているので、院内の展示の変化もお楽しみください。